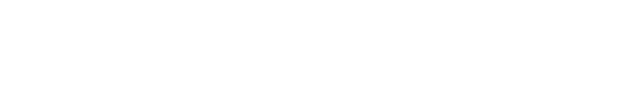多職種連携
ケアマネジャー・訪問看護師・地域連携室の皆さまへ
私たちはチームスピリットを大切にします。
ケアマネジャー、訪問看護師、地域連携室を始め、医療・介護に携わる多職種の方たちとのチームプレーにより、ご本人やご家族の価値観に寄り添いながら、ちょうどいい距離感で医療サポートを提供し、その人らしい暮らしを支えていきます。
チーム力が試される具体的なケース
- 病院への通院を拒否されているが、医療的ケアが必要な方
- 心不全があり、食事や生活習慣の指導が困難で、入退院を繰り返されている方
- がん終末期で、在宅での緩和ケア治療、看取りを希望されている方
- 末期腎不全で、高齢で透析を希望されず、在宅での看取りを希望されている方
- COPDで在宅酸素療法中の方が、肺炎で入院治療した後に、自宅退院された方
- 独居で、ベッド上のADLで、ご家族の介護がなく、毎日サービスが入っている方
- 認知症で、介護抵抗、暴力があり、何度もサービス事業者が変更になっている方
- 嚥下機能が低下し、誤嚥性肺炎を繰り返している方
非常に困難な事例に対しても、地域の多職種の方たちとチームを組んで協力して取り組むことで、解決の糸口を探っていきます。
多職種連携のために当院ができること
従来の電話やFAXだけでなく、リアルタイムで関係者同士の連絡ができる医療介護専用クローズドSNS(メディカルケアステーション)などの連絡手段を用いて、緊密に情報共有を図っていきます。
主治医意見書、訪問看護指示書は、ご連絡をいただいたら早急に作成いたします。
医学的に必要と判断された場合は、速やかに近隣の医療機関に紹介いたします。
在宅で実施可能な検査
- 血液検査、尿検査、便検査
- 喀痰培養、尿培養、真菌・白癬菌検査
- ポータブル超音波装置 (GE Vscan Air CL)
- ポータブル心電図
- HDS-R(長谷川式)
在宅で対応できる医療処置
- 点滴(末梢輸液、皮下輸液)
- 注射(骨粗しょう症治療薬など)
- 予防接種(インフルエンザなど)
- 在宅酸素の導入・管理
- たん吸引器の導入・管理
- 気管カニューレの管理
- 胃瘻、腸瘻、中心静脈栄養の管理
- 尿道カテーテル、膀胱瘻、腎瘻の管理
- 褥瘡管理、ストマ管理
- 麻薬管理(携帯型持続注入ポンプ「クーデックエイミーPCA」など)
病院に通院することが困難になっても、ご自宅でも同じ治療が受けられるようにお手伝いさせていただきます。
在宅での点滴は当院でもよく実施しておりますが、終末期の点滴についてはこちらのコラムをご参考ください。
終末期の点滴と平穏死について
老衰で、寝たきりとなり、食事や水分が取れなくなり、週単位の余命と予想されるとき、あなたは点滴を希望しますか。 また、あなたの大切な家族がそのような状況なら、点滴をしてほしいですか。 看取りの時期に点滴を行った場合、血管内 … 続きを読む
経鼻胃管については現在のところ対応しておりません。こちらのコラムをご参考ください。
連携医療機関(五十音順)
- 淡海医療センター
- 淡海ふれあい病院
- 近江草津徳洲会病院
- 済生会滋賀県病院
- 済生会守山市民病院
-
滋賀医科大学附属病院
-
滋賀県立総合病院
- 芙蓉会南草津病院
この他にも、県内の多数の医療機関と連携しています。
ご利用者さんが日常の療養生活を送る上で、専門的な検査や治療が必要になったときは、適切な医療機関へご紹介させていただきます。
また、自宅での生活が困難となった場合など、介護者の休息も兼ねて短期間の「レスパイト入院」の紹介もさせていただいております。
見学の案内はこちらです。
見学の案内